日本人の圧倒的多数、とりわけ高齢者のほとんどは、「死ぬときは病院ではなく、住みなれた自分の家で・・・」と願っているようです。
しかし現実には、自宅で死ぬ人は8人に1人にすぎません。つまり、現在の日本人の大半は、本人の望まない場所で死んでいることになります。なぜ本人の望み通りに自宅で死ぬことができないのでしょうか?
ひとつの理由は、病院が行う「延命治療」にあるということができます。たとえば末期のがん患者に対して、胃にチューブを通して栄養物を流し込んだり、24時間点滴を施したり、あるいは人工呼吸器を装着するなどの方法で、すでに生命活動を停止しようとしている人間を、機械的、強制的に生かそうとする・・・これが延命治療です。
しかしながら最近では、病院や医師が独断で延命治療を行うということは少なくなっています。最期が近づいたときの処置について、患者自身が意見をもつ場合はそれを聞き入れたり、患者の家族と話し合ってその希望を尊重するなどが、ますます一般的になっています。
多くのがん患者が病院で治療を受けつつ死ななくてはならないということは、一方で、現在のがん医療の限界をも示しています。患者が自宅で静かに死を迎えられる状態まで病状を回復させる、あるいは病状を安定させることができないのです。
しかしこのような現実の中でも、がん患者がなお在宅で療養できるようにしたい場合、それは不可能ではありません。ただしそれには、次のような条件が前提となります。
■患者自身が在宅で過ごすことを本心から望んでいる。
■病状がある程度緩和され、一時的であれ安定状態にある。
■患者が自分のおかれている環境や病状をよく理解している。
■患者を24時間介護できる人が存在する。
■過剰な延命治療は望まないという患者自身および家族の意志が明確になっている。
■自宅の比較的近くに、定期的な往診や緊急時の診療に対応してくれる医師がいる。
これらの条件がそろっていなくても、ほとんど自覚症状のないがんで、たまたま別の病気で検査を受けたときにすでに末期であることが判明した場合、残された時間を自宅で過ごさせめに帰宅させる、という形の在宅療養もあります。
在宅での終末療養を希望する声が増えるにつれて、最近では「訪問看護ステーション」もたくさん設立されています。これは「都道府県知事の指定を受け、在宅療養をする患者に対し、看設の独自性を生かして日常生活の援助をする看護職の事業所」で、すでに全国で5000カ所にのぼります。
また、病院が訪問看護サービスを行っている場合もあり、入院後に在宅療養を希望する場合は、主治医を介して申し込むこともできます。訪問看護を受けるには、月1回の主治医の診祭が必要となる他、理学療法士や薬剤師、栄養の訪問も必要時に受けることになります。
以上のように、現在の在宅療養は、積極的治療というよりは、むしろ看護や生活の質に重点がおかれています。日本ではこれまで、医療や看設は病院で行われるものという考え方に人々が慣らされてきました。
在宅療養の必要性はわかていても、実際には、医師が末期のがん患者を自宅に戻すことをためらうあるいは終末期の患者を自宅で世話することが困難であるという理由で、家族が患者の希望に積極的に耳を貸そうとしない、などの例が少なくありません。
逆に、訪問看護ステーションが各地に設立されていることを知り、十分な話し合いなしに、安易に患者を退院させて在宅療養に移す医師もいるようです。しかし残された人生の時間が限られている患者の心に十分配慮した在宅システムが実現するまでには、まだ時間がかかりそうです。
また、経済的な問題も軽視できません。これには、在宅療養に対して健康保険と介護保険のどちらを適用するか、「在宅末期医療総合診療料」の対象にするのか、がんの症状の緩和と積極的治療のいずれを選択するか、などの問題も関係してきます。
これは、患者の年齢、病状、介護環境などによって条件が大きく異なるため、選択は容易ではありません。経済的側面も含めた在宅ケア全体を相談できる専門家の育成が必要になる問題でもあります。
がん患者が自宅で過ごすには、他にも課題があります。たとえば、がんの痛みが現れた場合の対処法(鎮痛剤モルヒネの使用法など)、在宅ホスピス専門看設師の育成、看護や介護サービスの24時間化などの問題が、改善されなくてはなりません。
末期のがん患者が自宅で療養し、自宅で最期を迎えたいという希望は今後ますます高まると予想されるため、介護保険法の見直しをはじめ、がん患者の在宅療養システムを充実させる試みも、今後前進することが期待されています。
・・・
どうすれば、がんは治せるのか!?
標準治療(手術・抗がん剤・放射線)に耐え、代替療法も活用すれば・・・
本当にがんは治せる?
詳しくはこちらのページで
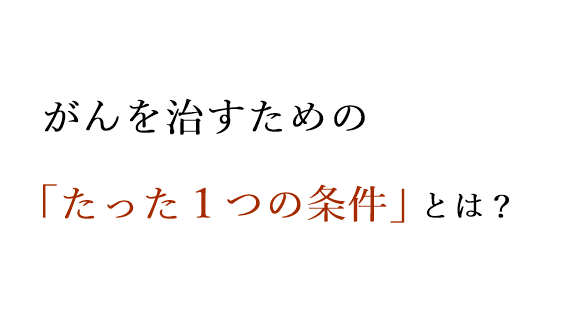 こちらのページで明らかにしています。
こちらのページで明らかにしています。